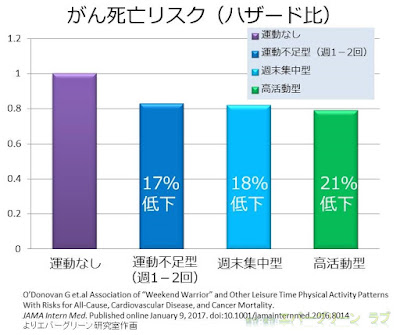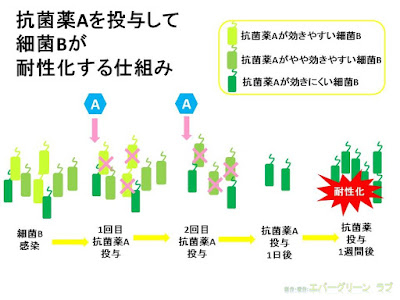忙しすぎることは、多くの場合、貨幣を得るために時間を割きすぎて、人生の様々なことに充分な時間がとれないということです。
例えば、営業の外回りに忙しいセールスマンや、残業して1日10時間以上PCの前で事務を行うOL、国際的に活躍するジェットセッターと呼ばれるようなビジネスマン、共働きで、職場と保育園を掛け持ちしながらなんとか子育てをこなすママ・パパなどの人々は、健康の基本である食事や運動にどれだけの労力と時間を費やせるというのでしょうか?
忙しいことが常習化され、そのようなライフスタイルが定着すると、心身の健康にかなり影響することが解明されてきています。
今日は、そんな中でもちょっとショッキングな、(超)加工食品の摂り過ぎでがんになるようだとの研究をご紹介して、時間の使い方=ライススタイルについて考えてみたいと思います。
超加工食品の消費とがん発症リスク
Thibault Fiole et.al. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: resultsfrom NutriNet-Santé prospective cohort.【研究の参加者と方法】
●参加者:18歳以上の健康なフランス人104,980人(平均年齢42.8歳、女性78.3%)
●参加者は、6か月ごとに、2週間(1週末を挟む)の食事内容を24時間オンライン食事アンケートに応答して、食品3,300種類について普段の摂取量を測定し、最低でも2日間の記録が必須とされ、これを完遂できた人々を解析の対象とした。
●上記の食品はNOVAという食品の加工の程度の分類に従って、
①未加工:未加工ないしは最小限の加工の食品
②調理食:素材を家庭で使用する調味料で調理した食品(油漬けや酢漬けなどの保存食品なども含む)
③加工食品:缶詰、瓶詰、塩や砂糖を加えたナッツ、砂糖漬け食品、燻製肉、チーズ、パン屋で売っているパンなどで、抗酸化剤(ビタミンCやEなど)、防腐剤、食塩など、食品を長持ちさせるための添加物を含む食品。ビールやワインなどの①の未加工食品を発酵させて醸造したアルコール飲料はこのグループに属する
④超加工食品:
・抗酸化剤(ビタミンCやEなど)、防腐剤、食塩、安定化剤(ジャムのペクチンなど)、砂糖など5種類以上の添加物を加えている食品。
・カゼイン、乳糖、ホエイ(プロテイン)、グルテン、水素添加油脂、エステル交換油脂、 加水分解蛋白質、大豆プロテイン、マルトデキストリン、転化糖、高果糖コーンシロップ、色素、香料、炭酸飲料、砂糖以外の甘味料(人工甘味料も含む)などを含む加工食品。
・これらを代表する食品として、スナック菓子、アイスクリーム、キャンディー、大量生産されたパッケージ入りのパン、マーガリン、(パンなどににつける)スプレッド、ケーキ、ケーキミックス、シリアル(コーンフレークなど)、エナジードリンク、エネルギーバー、砂糖・果糖入り飲料、フルーツ飲料、ココア飲料、乳飲料(カフェオレ・イチゴオレなど)、インスタントソース(カレールー・パスタソースなど)、ピザ、フィッシュやチキンナゲット、ハンバーガー、ホットドッグ、ハム・ソーセージ・ウインナーなどの加工肉、カップ麺、インスタント食品、インスタントスープ、インスタントデザートなど
・ウイスキー、ジン、焼酎などの蒸留酒はこのグループに属する
以上の4つのグループに分類し、参加者が食べているものを分析した。

●患者の申告と、それを裏付ける医療記録、国の疾病データベースを利用し、参加者のがん発症を平均5年以上追跡して確認した。
●年齢、性別、教育レベル、がんの家族歴、喫煙の有無、身体活動レベルなどのがんのリスク因子で調整を行った。
【研究の結果】
●食事中の超加工食品の割合が10%増加すると、全がんのリスクが12%上昇した (2,228人の解析、ハザード比 1.12、95%信頼区間 1.06~1.18、 P<0.001で統計学的に有意)
●食事中の超加工食品の割合が10%増加すると、乳がんのリスクが11%上昇した (739人の解析、ハザード比 1.11、95%信頼区間 1.02~1.22、P<0.02で統計学的に有意)
●前立腺がん、結腸直腸がんに関しては、統計学的に有意な関連はなかった。
●これらの結果は、食品中の栄養の質(脂質、ナトリウム、炭水化物摂取、西欧食)などの調整因子で補正後も統計学的に意味があるものだった。
●②の調理食の多い食事内容だった人のグループは、がんリスクの上昇は認められなかった。
●食事中の、①の未加工の割合が10%増加すると、全がんのリスクは58%低下することが認められた。(102,752人の解析、ハザード比 0.42、95%信頼区間 0.19~0.91、 P<0.03で統計学的に有意)
●食事中の、①の未加工の割合が10%増加すると、乳がんのリスクが約10%低下することが認められた。(2,228人の解析、ハザード比 0.91、95%信頼区間 0.87~0.95、 P<0.001で統計学的に有意)
●超加工食品の内訳は図の通りだった。

超加工食品はがん発症を招く
いかがですか?ちょっとライフスタイルを考え直すきっかけのような研究ですね。
超加工食品の摂り過ぎはがんを招き、一方、自分で調理して、素材を生かした食事をすればがんになりにくいということです。
この研究では、仮説として次のことが原因で超加工食品ががんを増やすのではないかと指摘されています。
●超加工食品には、栄養成分以外に合成化合物が含まれ、加熱処理によりメイラード反応が起こりその結果、アクリルアミド、ヘテロサイクリックアミン(HCA)、 多環芳香族炭化水素(PAH)などの発がん性物質が生成される。
●超加工食品には、ビスフェノールAなどの発がん性がありホルモンに類似した内分泌攪乱物質も含まれることがある。
●規制当局に添加物として認可されてはいるものの、摂取した場合に健康上で議論のある、加工肉に含まれる次亜硝酸ナトリウムや、酸化チタン(白色剤)などは動物モデル、細胞モデルで発がん性が示されている。
加工食品があまり体に良くないことは分かっていても、サラリーマンなど勤めがあると、忙しいので、つい加工食品やファストフード、ファミレスなどの外食、コンビニ中食、お弁当などで済ませてしまうことが多いと思います。
産業革命以降の文化的な生活は、ライフラインなどのエネルギーや、衛生などヒトの生存に有利な技術をたくさん生んできました。
しかし一方で、資本主義・貨幣経済に代表される社会システムは、ヒトが貨幣や物品、安心という見えない「価値」に脅迫されるようにして、「人生」という貨幣や保険では代替できない「ヒトに許された時間=寿命」を消費させるようにしています。
そのような「価値」も、人生の時間が短ければ=早死にしてしまえば、意味のないものです。
本当の「価値」とは健やかで楽しい生命力にあふれた時間を多く持つことではないでしょうか?
私も勤め人だった期間が長かったですが、ファストフードやコンビニ食などを美味しいと思って利用したことはありません。
ファストフードやコンビニ食はあくまで時間を節約するために利用していたと思うのです。
現在の社会を生きぬいてゆく上で、健康には良くないと分かっていても、忙しさを理由にそれらのものを利用せざるを得ない状況が多すぎると思います。
⇒米国マクドナルド が抗生物質与えた鶏肉の使用をやめる
せめて、生命の本質の1つである、「食べること」にもっと時間をかけて、丁寧に、美味しくいただこうではありませんか。
忙しく時間を節約するライフスタイルが、かえって寿命を短くする食事内容につながるのはこれではっきりしたようです。
さあ、せめて今晩は、定時に帰って、自分で好きな料理を作って、ゆっくりと美味しく味わいましょう。
エネルギー効率のよすぎる食事は考えもの
最後に、円グラフの超加工食品の内訳をご注目ください。超加工食品は主に糖質で、飲料などの割合が多いことがわかります。
超加工食品の占める割合が多い食事では、インスリンが多く追加分泌され、血糖値も高止まりしやすいでしょう。
そこに、上記の発がん性物質や内分泌攪乱物質が発がんの引き金になって、がんとなるのでしょう。
言うまでもなく、血糖値の高い糖尿病やその予備軍でのがんの罹患率は高いことが分かっています。
⇒糖尿病予備軍は癌リスクが15%高い
 |
| バナナとバナナジュース、どちらがヘルシーだと思いますか? |

 「エネルギー効率の良すぎる食事」は控えめにするべきですね。
「エネルギー効率の良すぎる食事」は控えめにするべきですね。⇒『主食の重ね食べ』は肥満のもと