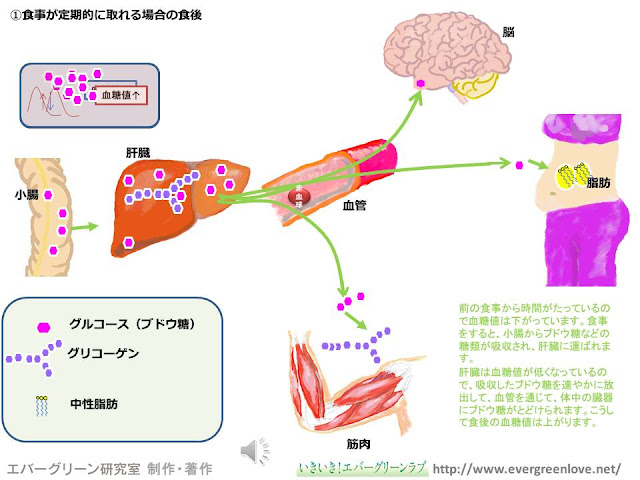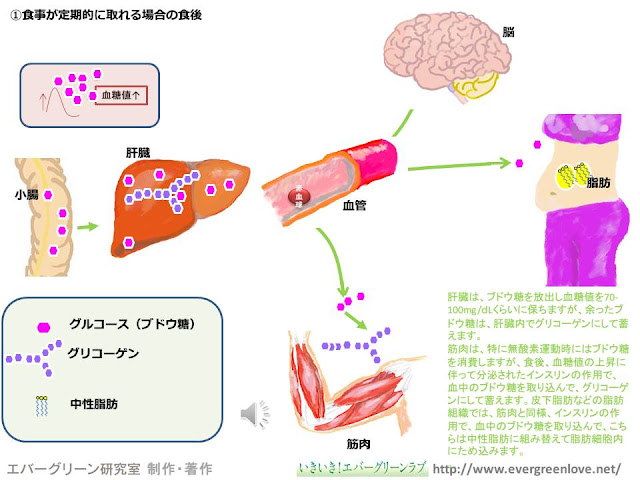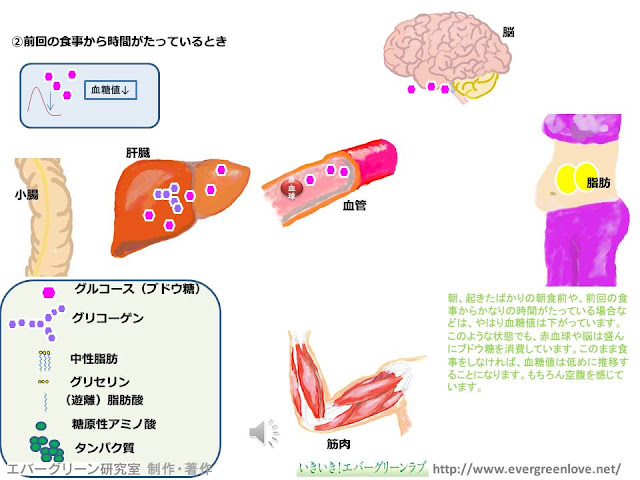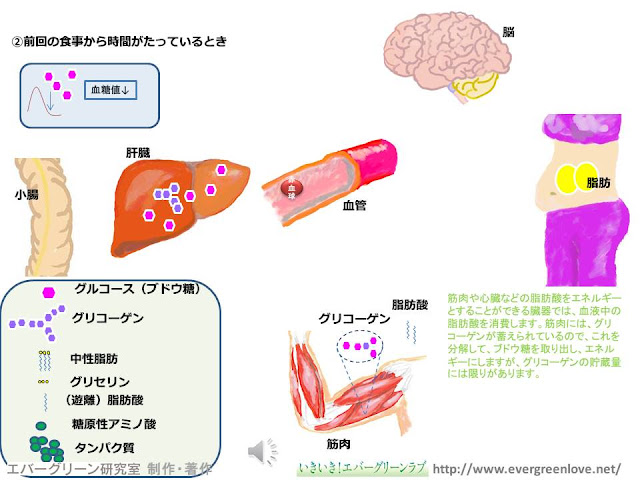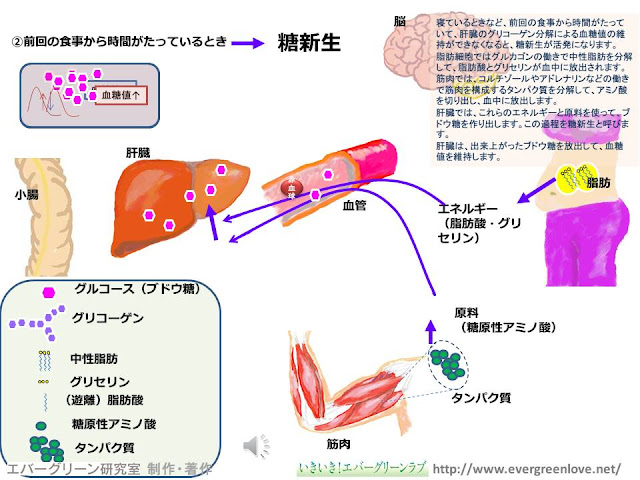スウェーデンで45年間にわたり、死亡リスクを増やす原因について調査をしたところ、第1位は喫煙であることが認められました。
スウェーデンで45年間にわたり、死亡リスクを増やす原因について調査をしたところ、第1位は喫煙であることが認められました。ここで問題です。
喫煙に次ぐ第2位は、次のうちどれでしょう。
- 血清コレステロール高値
- 運動不足
- 高BMI
中年男性の45年間の死亡リスクに影響を及ぼす因子について
Per Ladenvall et.al.; Low aerobic capacity in middle-aged men associated with increased mortality rates during 45 years of follow-up.【研究の方法】
- 1963年に50歳だった男性の792人のデータを使用した、45年間にわたる前向き観察研究(プロスペクティブコーホート研究)。
- 参加者が54歳の1967年に、792人のうち656人が自転車(エルゴメーター)に乗ってマスクをつけて、最大酸素摂取量(VO2max)を測定して、運動能力の上限を測定した。
- 2012年の99歳まで参加者を観察して、約10年ごとに運動能力検査をした。
- 参加者の死亡および一般国民の死亡率は、スウェーデン国民死亡原因登録のデータで確認した。
- 参加者の身体測定・血圧や血液検査データと、運動能力と死亡のデータを比較して分析した。
- 運動能力の指標である最大酸素摂取量(VO2max)で、次の3つのグループに分けて比較した。
- VO2maxが高いグループ
- VO2maxが中等度のグループ
- VO2maxが低いグループ
- VO2maxが高いグループは、特に運動しない場合と比べ45年間の死亡リスクが21%低下すると推算できた[ハザード比0.79 (95%信頼区間0.71–0.89; p < 0.0001)]。
- つまり、運動しないと45年間で21%死亡しやすくなるといえる。
- 運動しないことの死亡リスク増加へのインパクトは、喫煙に次いでの2位で、高BMI、血清コレステロール高値などよりもはるかにリスクが高かった。
- 喫煙での死亡リスク増加は58%の上昇であった[ハザード比1.58 (95%信頼区間1.34–1.85; p < 0.0001) ]。
この研究は45年にわたる長期間参加者の656人を追跡して、10年ごとに運動テストも実施しているのでかなり信頼できる研究結果といえるでしょう。
現在では、喫煙は最もはっきりした健康へ悪影響のあるリスクの1つです。
運動不足はその喫煙に次いで、死亡リスクを上げてしまうのです。
エバーグリーン研究室では、運動の習慣をつけることが、生涯の健康にどれほど良い影響を与えるかについて、皆さんといろいろ勉強してきました。
でも、運動不足がどれだけのデメリットであるかについては、解説するのが難しいところでした。
この研究で、実感いただけたでしょうか?
禁煙に成功した方、次は運動習慣ですね。
運動のメリットを復習
運動することを習慣にできれば、まず筋肉が太目に維持され、筋肉内のミトコンドリアが増加し、その働きが向上します。筋トレと有酸素運動を組み合わせた適度な強度がお勧めです。
肩こり、腰の痛み、関節痛など、筋肉がつくだけで解消できる痛みも多くあります。
また、有酸素運動をして心拍数を上げると血流がよくなり、肺や心臓や血管の健康にも役立ちます。
定期的に骨が刺激を受けることで、骨も強くなります。
代謝が上がるので、体の中の不要なものが排泄されやすくなり、何より太らず健康に美味しいものを楽しめます。
また、運動ががんや認知症などいろいろな病気を予防する証拠も数多くあります。
さらに、適切な運動で病気を回復に向かわせたり、進行を遅らせることさえできます。
エバーグリーン研究室では、健康な生活の基礎となるのが、運動習慣と考えています。
どんなダイエットや健康法、サプリメントや薬も、適切な運動習慣の効果にはかないません。
また、これらのダイエットや健康法も、運動と組み合わせなければ効果が発揮されないと考えて間違いありません。
キーワードは、
- 筋肉の量が増加
- ミトコンドリアが増加して活性化
- 有酸素運動+筋肉トレーニング
- 心肺機能向上(血流を良くする)
- 動脈硬化予防
- 骨の健康
- 肥満回避
- 代謝向上
- 老廃物除去(デトックス)
- 汗をかく能力(熱中症予防)
- 体温調節
- 自律神経活性化
- 認知機能改善(ボケ防止)
- 精神の健康
- がん予防
- メタボ防止(血圧、血糖値の正常化)
関係する話題は、下記をご参照ください。
ミトコンドリアの数で若さが決まる
有酸素運動と無酸素運動の違い
体重・BMIより筋肉量が大事
運動すると食べ過ぎる?
デスクワークは危険!
座り時間を短くすれば老化しにくい
筋肉は脚から落ちる
1時間に2分体を軽く動かせば寿命が延びる
ミトコンドリアが活発な筋肉を保つためには
運動すればボケを防げる!
歳をとってから運動を始めても遅くはない
BMIが正常でも死亡率が上がる原因?
運動不足で脳がしぼむ!